トランプ大統領との関係が微妙で最近は冴えないイメージのイーロン・マスクだが、やっぱりすごい面があると分からせてくれる話があった。
これは面白い話だよな…。イロン・マスクのSpaceXは宇宙船のドッキング部分をマウンテンバイクの部品から作り上げたが、NASAは最初から独自の部品を作ろうとした。これじゃNASAに勝ち目はない。https://t.co/Foja1vXHjZ
— Kazuto Suzuki (@KS_1013) 2025年9月18日
リンク先のワシントンポストの記事をChatGPTに訳してもらった。
使ってるChatGPTはフリーなので途中で制限が掛かり5時間中断させられた。
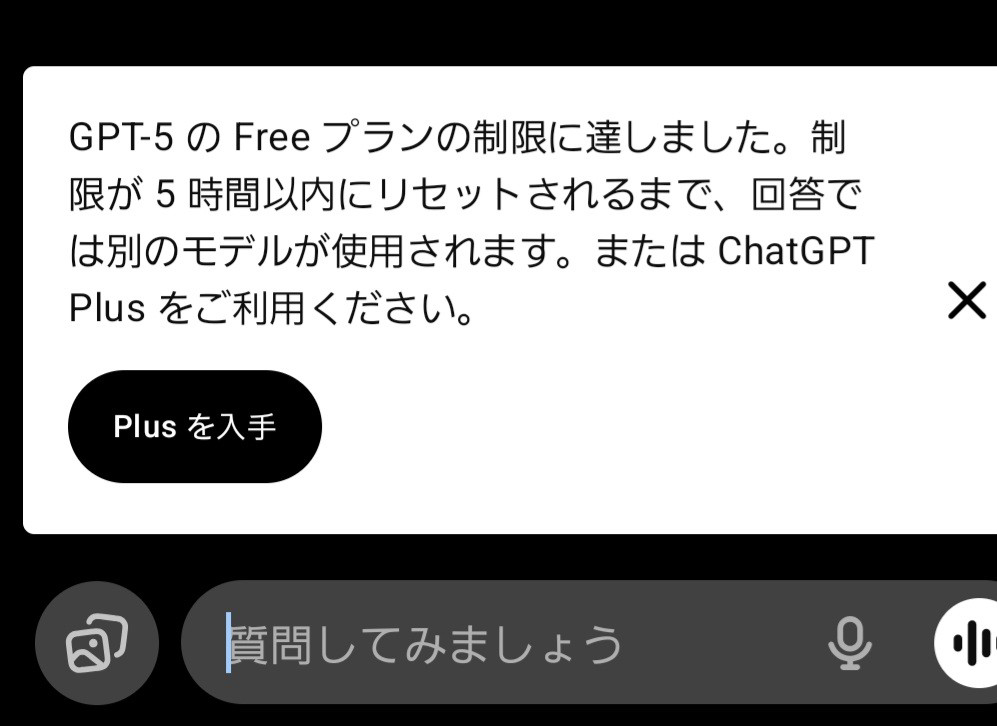
~~以下はChatGPTの訳~~
NASAの技術者たちは、スペースXがわざわざ自前でドッキングシステムを作ろうとすることに困惑していた。
宇宙機関(NASA)は、ボーイングと提携して10年以上にわたりドッキングシステムの設計に取り組んでおり、それをスペースXに無償で提供していた。宇宙ステーションとのドッキングは危険を伴う作業であり、NASAは自らのシステムが安全に機能すると確信していた。スペースXがしなければならないのは、それを取り付けることだけだった。
マスクの指揮のもと、その会社は一部の人々が「アルゴリズム」と呼んだ方式に従って運営されていた。それはスピード、効率、革新を推進するための方程式のようなものであり、その後の年月において、再使用可能なロケットの開発のように業界の他の企業が解決しようとすらしなかった課題を克服し、業界を支配する原動力となった。このドッキングシステム再設計のこれまで語られてこなかった物語は、マスクとスペースXのチームがどのようにして産業を揺さぶり、次の10年で従来の航空宇宙企業を凌駕する文化を築いたのかを説明する手がかりとなる。
スペースXは現在、数日に一度の頻度でロケットを打ち上げており、その回数は既存の競合他社や中国をも上回っている。同社の「ファルコン9」ロケットは主力機となり、「ドラゴン」宇宙船はNASAが宇宙飛行士を宇宙ステーションへ送る唯一の手段となっている。またスペースXは、国家安全保障衛星を打ち上げる上で国防総省にとっても不可欠なパートナーとなった。
NASAのドッキングシステムを評価する任務を担ったのはジャレット・マシューズで、当時36歳のエンジニアだった。彼はスペースXに加わる前、ほぼ10年間にわたりNASAのジェット推進研究所(JPL)で働いており、スペースXではマスクから「完全な自由裁量権」を与えられて革新に挑んでいた。
初めて精査した時点で、NASAのドッキングシステムは極めて堅牢であることは明らかだった。というのも、それは複数種類の宇宙船で使用できるよう設計されていたからだ。しかしマシューズは、そこにいくつか手を加えれば、ドラゴン専用の、よりシンプルで洗練された設計を作れるのではないかと考えた。しかも重要なのは、それが機体に過度な重量を加えないようにできることだった。
「大幅に単純化できる余地があったんです」とマシューズは振り返る。
他の会社なら、そんな考えはおそらく笑い飛ばされたに違いない。
――若いエンジニアがNASAの設計を改良するだって? 本気で?――
だが、スペースXは「ファースト・プリンシプル(第一原理)」の哲学に基づいて動いていた。それは革新をめぐる哲学であり、シリコンバレーの多くの人々の間でも流行しつつあった考え方だ。スペースXの創業者イーロン・マスクが語ってきたように、その狙いは「物事を物理学的に、根本的な真理にまで還元し、そこから積み上げて考えることであり、類推によって考えるのではない」というものだった。特に「新しいことをやろうとするとき」にこそ重要だとマスクは強調していた。
複雑さはしばしば信頼性の証とみなされがちだったが、それは誤りだとスペースXの打ち上げ担当副社長キコ・ドンチェフはある会議で断言した。
「最もシンプルなものこそが最良の設計であり、最も信頼できることが多い。複雑さは“悪魔”だ、と私たちはよく言います。製品から部品を取り除き、最適化し、単純化することに多くの時間を費やすのは極めて重要なのです。」
マシューズがドッキングシステムの評価を任されたのは、スペースXに入社してまだ数か月しか経っていない頃だった。だが、その短い期間で彼は、自分の仕事が安易な道を選ぶことではないと理解していた。彼の役割は「アルゴリズム」を適用し、世界最高のドッキングシステムを設計することだった。たとえそれが、NASAの宇宙飛行士輸送をめぐってボーイングと競っている最中に、宇宙機関のシステムを拒否することを意味したとしても。
彼はインターンと協力しながら「マックドッカー」プロトタイプのスケッチを描き始めた。NASAのシステムとの主な違いは「ソフトキャプチャ」設計にあった。これは、ラッチ付きのリングを最初に伸ばして宇宙ステーションのポートに差し込み、わずかなずれを調整できる柔軟性を持たせた部分である。宇宙船がドッキングの際に非常にゆっくりと動いているとはいえ、リングは最初の接触を吸収し、その後微調整ができなければならない。そしてソフトキャプチャが完了すると、12個のラッチが固定され、宇宙船をステーションにしっかりと結合する。この工程は「ハードキャプチャ」と呼ばれる。
NASAの設計では、ソフトキャプチャ用リングを所定の位置に動かすために6本の機械アーム(アクチュエータ)が用いられていた。これらのアームはバネのように機能するようプログラムされており、宇宙船がステーションに接触した際の衝撃を吸収できるようになっていた。しかし、それは複雑で、大量の電力を必要とし、重量もかさんだ。さらに、そのアームを制御するソフトウェアや電子機器が故障すれば、ドッキング全体が失敗に終わる可能性があった。
マシューズとインターンのクレイグ・ウェスタンは、マウンテンバイク用のスプリングを使った、よりシンプルな設計を開発した。これにはソフトウェアも電子機器も不要だった。
プロトタイプが完成すると、マシューズとウェスタンはそれをマスクの最も信頼するエンジニアの一人、マーク・ジュンコーサに見せた。社内にはマスクと直接やり取りするのを避ける者もいたが、ジュンコーサは上司を恐れていなかった。彼はマシューズに「これはマスクが見たがるものだ。今すぐ彼に見せに行こう」と言い、二人はアポなしで「マックドッカー」をマスクのデスクへ運び込み、その場で見てもらうことにした。
マスクは熱心に観察し、ドッキングリングを引っ張ったり押したりしながら顎に手を当てて考え込んだ。そして数分後には「よし、これで行こう」と言った。議論もなければ、ほかのエンジニアとの協議もなかった。メモも会議も不要だった。マスクは気に入り、その場で即決したのだ。
「スペースXでは、一度ゴーサインが出れば、その方向に時速百万マイルで突っ走れるんです」と、現在は月面探査ローバーを開発するアストロラボのCEOとなったマシューズは語る。「あれこれ悩んだりはしません。ただすぐに動き出すんです。」
「呆然とした視線」
スペースXがNASAのソフトキャプチャ設計を拒否し、自前で独自のものを作ろうとしていることに、NASAは信じられない思いだった。
マシューズが上司とともにヒューストンへ飛び、NASAの技術者たちと会って自分たちの設計を提示したとき、彼らが返してきたのは「呆然とした視線」だったと彼は振り返る。
「彼らの目の奥に見えたんです。『こいつらはバカだ。自分たちが何に手を出しているのか全然わかってない』って考えているのが。だって、彼らはこの問題に20年を費やしてきたんですよ。その頭の中で『お前たち、いまから何をやろうっていうんだ?』って声が聞こえてくるようでした。」
もしNASAの懐疑心を乗り越えられなければ、スペースXは商業有人宇宙船(Commercial Crew)契約を失うかもしれない――マシューズはそう恐れた。そして、それは自分の責任になるのだと。
契約決定を前にした数か月間、NASAは依然としてスペースXを宇宙飛行士輸送に信頼できるとは考えていなかった。むしろ新しいドッキングシステムを「提案の弱点」と見なし、懐疑心をさらに強めていた。マシューズはNASAに対して文書で反論を送ったが、それでも疑念は拭えず、NASAはケネディ宇宙センターで宇宙船について話し合う会議を求めてきた。
窓のない、まるでアポロ時代に整えられたかのような部屋で、NASAの契約評価チームは大きなテーブルを挟んでスペースXの技術者たちと向かい合っていた。スペースX側はまるで博士課程の学生が論文審査に臨むように落ち着かず、身じろぎしていた。
マスクは会議を、NASAが経験しているパラダイムシフト――長年スペースシャトルで有人飛行を続けてきた後、人類宇宙飛行を民間企業に委ねるという変化――を認める言葉で始めた。しかし同時に、スペースXはその「神聖な信頼」を真剣に受け止めると保証した。彼らしい誇大な言い回しで、この任務は国家にとってだけでなく人類全体にとっても重要なものであり、真に「宇宙に進出する種族(spacefaring species)」になるための道なのだと語った。
マスクが見守る中、マシューズは不安を抱えながら自分のドッキングシステムについて詳しく説明を始めた。約30億ドル規模の契約の行方は、このプレゼンにかかっていた。しかし、図表やグラフを示すことができたこと、そして彼自身がそのシステムを心から信じていたことが、説明を後押しした。確かにそれはよりシンプルな設計だったのだ。会議を終えたマシューズは、ついにNASAの考えを変えることができたと自信を持って感じていた。
そして2014年9月、NASAはアメリカで有人宇宙飛行を復活させる契約を2社に授与すると発表した。スペースXと、NASAが好んでいたドッキングシステムを採用していたボーイングである。
だが、それはスペースXがボーイングより先に――あるいは本当に――宇宙飛行士を飛ばすことを意味するものではなかった。
「NASA全体での支配的な意見は『ボーイングなら間違いない。実績も歴史もある大手航空宇宙企業だから』というものでした」と、スペースXでの飛行を割り当てられていた元NASA宇宙飛行士のダグ・ハーリーは振り返る。「そしてスペースXという“第2の提供者”が手に入れば、それはボーナスだ、という感覚だったんです。」
スペースXでの飛行任務を割り当てられることは、多くの宇宙飛行士団にとって、せいぜい行き止まりに過ぎないと考えられていた――なぜなら、彼らは実際には飛ぶことがないだろうと思われていたからだ。むしろそれは「死刑宣告」に等しいとも言われた。スペースXがもし飛行したとしても、「殺されなければ幸運だ」と考えられていたのだとハーリーは語る。
「NASA全体で、我々が成功すると思っていた人間なんて、多く見積もっても5人くらいしかいなかったでしょう。」
さらにハーリーは、スペースXでは宇宙飛行士を貨物のように扱う、と言われたこともあったという。宇宙飛行士は「生物学的ペイロード(生体貨物)」に過ぎないのだ、と。
それは逆に、ハーリーの決意を強めることになった。彼はすでに数年をかけてスペースXのチームと親しくなっていた。確かに彼らは若く、やり方も従来とは違っていた。だが、宇宙船を一から作り上げていく姿を見て、彼は彼らを尊敬するだけでなく、信頼するようになっていた。
当初、NASAの多くはスペースXが独自にソフトキャプチャ式のドッキングシステムを開発できるのか懐疑的だった。しかしマシューズとそのチームの取り組みを見守る時間が長くなるにつれ、その疑念は和らいでいった。スペースX本社を訪れたNASAの技術者たちは「マックドッカー」の試作機を観察し、感銘を受けた。また、マシューズのチームが数週間単位でヒューストンのジョンソン宇宙センターに入り込み、NASAの技術者と共に宇宙ステーションのモックアップを使ってドッキングを模擬し、450回以上の試験と数千回に及ぶコンピュータシミュレーションを行ったことも信頼を高める一助となった。
「NASAの人たちはシステムの挙動を目の当たりにし、少しずつ我々のファンになってくれたんです」とマシューズは語る。
「絶対に恐ろしかった」
しかしドラゴン宇宙船が宇宙飛行士を乗せる前に、まず無人の試験飛行「デモ-1」を成功させる必要があった。この無人飛行では、自律型の宇宙船がロケットから分離し、時速1万7500マイル(約2万8000km)で周回する宇宙ステーションに追いつき、自らドッキングする――そしてマシューズのシステムを、初めて実際の宇宙環境で試すことになるのだった。
2019年3月2日の打ち上げは順調に進んだ。しかし、自律ドッキングは依然として大きな難関だった。マシューズは「本当に恐ろしくて仕方なかった」と振り返る。
ドラゴンのドッキングとは、要するに「宇宙ステーションに突っ込むこと」だったのだ。「制御された衝突ではあるけれど、衝突であることに変わりはない」と彼は言う。つまりそれは、「2万ポンド(約9トン)の乗り物を、1000億ドル規模の国家的研究所にぶつけるようなもの」だったのだ。
やがてドラゴンはスムーズかつ安定してステーションへと接近し、ついにはそっと寄り添うように静かに接触した。それはまるでやさしいキスのようだった。
カリフォルニアにあるスペースXのミッションコントロールセンターのコンソール席で、マシューズは腕を頭の上で組みながら、人生でこれほどまでに緊張したことはないというほどの不安に包まれて見守っていた。
その隣には妻であり、デモ1ミッションマネージャーのアールティ・マシューズが座っていた。もしドッキングがうまくいかなければ、雇い主だけでなくパートナーである彼女まで失望させてしまうことになる。
「ソフトキャプチャ確認」――ミッションコントロールのディレクターがそう声を上げると、マシューズは立ち上がり、同僚たちとハイタッチを交わした。彼の発明が成功したのだ。
~~訳ここまで~~
全く新しいものを作ることだけがイノベーションではなさそうだ、既存の完成形に無駄や過剰な要素があればそれを削ぎ落とす、そういう作業もイノベーションに通じるのだ、何だか現代版コロンブスの卵のようでもある。